結露・水漏れクレームを“見える化”で減らす。今日の一台から変える現場設計
ここ数年、梅雨から真夏にかけて「室内機の水滴」「クロスの染み」「床が濡れる」といった問い合わせが目に見えて増えています。空気が湿り、機器は高能力化し、現場は繁忙期でスピード勝負。この三つが重なると、技術の差が顕著に表れドレンや断熱の小さな妥協が一気に表面化します。
エアコン業者 募集やエアコン工事業者 募集で出会う協力業者様に大きな事故に至った事例や原因を共有し、再訪ゼロに近づけるために尽力しております。
なぜ今クレームが増えているのか(環境・機器・スピードの三重要因)
露点と風量低下が招くオーバーフローの仕組み
結露は偶然ではなく物理です。湿った空気が露点温度を下回る表面に触れると水になります。最新機は省エネ性が高くコイルがよく冷える一方、微風運転やフィルター目詰まりで風量が落ちるとコイル温度が下がりすぎ、霜と解氷が繰り返されて一時的に水量が跳ね上がります。露点に触れやすい環境と冷えやすい機器が重なると、ドレン経路の弱点が一気に噴き出します。
繁忙期の時短施工が生む“見えない”水封
忙しい日ほど水平確認や勾配の最終チェック、貫通部の気密処理、断熱の巻き終わりなど地味な工程が雑になりがちです。室内機より低い貫通位置で“いったん上がる”ラインができれば、そこが水封になり逆流します。“たるみ”や蛇行も同様で、見えない区間の小さな妥協が翌日の再訪につながります。
水の通り道を設計し直す(ドレンは「設備」だという発想)
勾配と立ち上がりの基準を現場で再現するコツ
ドレンは付属品ではなく“設備”です。経路は線で考え、一定勾配で落ち続けることを設計段階で決め切ります。室内機のドレン口より貫通位置を必ず下げ、勾配の逃げを確保します。天井裏など点検しづらい区間は、ホース任せにせず形が崩れないよう管材で固定し、沈み込みや蛇行の余地を断ちます。屋外先端は外壁から離して自由落下を確保し、風圧や表面張力の戻りを避ける角度を保ちます。
露点をまたぐ区間の断熱厚・継ぎ目・気密の作法
露点をまたぐ部分を“冷やさない”ことが重要です。断熱は厚く、配管は短く、継ぎ目を作らずに一気に巻き切ります。巻き終わりは重ね幅を十分に取り、経年でほどけない材料を選びます。貫通部はスリーブで空気層を分け、室内側はパテで気密を高めて外気の侵入を止めます。ここが曖昧だと壁内で配管が汗をかき、クロスに染みが出ます。
また、断熱材をビニールテープで強く巻きすぎると断熱効果が低下し、結露の原因になるので強く巻かないようにすることも大切です。
再訪を最短化する診断フローと復旧の作法
室内機レベル → 通水テスト → 貫通部 → 屋外先端の順番
ご存じのエアコン業者様も多いと思いますが、再訪の際に現地で迷わない鍵は切り分けの順番です。最初に室内機レベルとドレンパンの水位、フィルターと熱交換器の汚れ、凍結痕の有無で機器側の要因を切り分けます。次に透明ホース区間で通水し、排水速度と気泡混入の有無から勾配や閉塞の気配を掴みます。貫通部の断熱・パテ・スリーブの状態を触診と目視で確認し、天井裏は点検口から冷たさを拾って結露の有無を推定します。
しかし、ほとんどの場合は目視で結露部分が分かることが多いので迷うことは少ないと思います。
最後に
近年の高温化、商品の省エネ化、住宅の気密性の向上など様々な要因により結露によるクレームが増加傾向にあります。
そのため、一昔前では必須ではなかった貫通スリーブが必須となっていることや、室内機の内パテもメーカの据付基準に明記されるようになりました。
エアコン工事業者様への工事負担が増えてきているのが現状です。しかし、昔と同じような工事をしていればそれは「変化できないエアコン業者」として、真っ先に切り捨てられてしまう可能性があります。
環境と時代に合わせた施工を行うことが大切であるとともに、ご自身の評価を高める方法でもあります。
また、弊社ではエアコン工事協力業者様を常に募集しております。閑散期に稼ぐためにスキルアップすることも可能です。
昔と違い、エアコン工事のみでは稼ぐことが難しくなっているので、向上心のあるエアコン業者様からのご応募をお待ちしております!
お問い合わせはコチラ
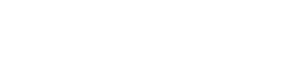

コメント